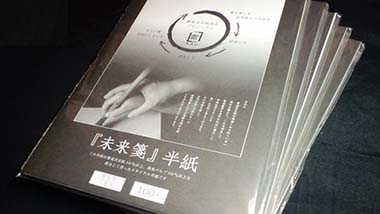文房四宝の学習所・研舎を主宰する著者が、
長年の研究を通じて得た「文房四宝こぼれ話」を披露します。
ときには、「文房四宝こぼれ話」の、さらなる「こぼれ話」になることも?
連載をはじめてお読みいただく方は、最初に「前説」をご一読のほど。
文房四宝の学習所・研舎を主宰する著者が、長年の研究を通じて得た「文房四宝こぼれ話」を披露します。ときには、「文房四宝こぼれ話」の、さらなる「こぼれ話」になることも? 連載をはじめてお読みいただく方は、最初に「前説」をご一読のほど。
第8回 和墨事始 その1 曇徴さんにあらず
ある日、電話でこんな質問を受けた。
「今、韓国の新聞社が来ていて、「日本の墨作りは韓国から伝わったものですよね。曇徴さんは韓国の人だから」、と言うんですが、そうだと答えて間違いないですか?」
どうやら韓国の新聞に掲載されるらしく、慎重を期しての問い合わせらしい。で、私はこう答えた。
「おそらく韓国から伝わっていると思いますが、曇徴がはじめて日本へ製墨法を伝えたわけではないので、そこは注意してください。」
きっと、この答えを聞いた受話器の向こう側は、眉間に皺を寄せていたに違いない。
さて、日本の史書に登場する最初の製墨に関する記述は、『日本書記』に記載された推古18(610)年の高麗僧・曇徴の事績である。和墨を語る多くの書籍などで取り上げられて、時には曇徴が来て墨の製法を教えてから和墨が始まったように書かれることもある。しかし、それは大きな間違いなのだ。なぜなら、推古18年の記載自体が、曇徴が最初とは書かれていないのだから。
推古十八年春三月、高麗王貢上僧曇徴法定、曇徴知五経且能作彩色及紙墨、幷造碾磑、蓋造碾磑始于是時歟。
推古十八年の春三月、高麗王は僧の曇徴法定を貢上す、曇徴は五経を知り且つ能く彩色及び紙墨を作る。ならびに碾磑を造る。蓋し碾磑造りはこの時より始まるか。
「碾磑」は今の石臼のこと。石臼の製法は、この時に始めて伝わったかも知れないと言い、その他の「彩色」「紙」「墨」に関しては何も書かれていない。しかし、文意からいって、その他のものが始めてではないから書いていないと考えるのが、妥当というものだ。
製墨に関する最初の記述が、始めてではないという内容。和墨に関して何かを書こうとする者にとっては、どうにも煩わしい事実である。煩わしいので、ちまちま説明するよりも、端折ってしまうに及くはない。結果、あたかも曇徴が最初のような誤解を生む記述がしばしば蔓延ることになる。
和墨の歴史というのは、初手から蹴躓く感が否めない。
意味不明の法定と行方不明の曇徴さん
それにしても、『日本書紀』推古18年の曇徴に関する記載は、摩訶不思議な文である。そもそも、曇徴は日本に来たのだろうか?
もう一度、よく読んで欲しいのだが、高麗王が貢上したのは、「僧曇徴法定」である。肝は「法定」とは何かなのだが、困ったことにそれに関しては一言半句も書かれていない。
人である僧侶を貢ぐというのも、現代の私たちからすると、ちょっと違和感があるのだが、それについては推古33年にも事例がある。
卅三年春正月壬申朔戊寅、高麗王貢僧惠灌。仍任僧正。
三十三年春正月壬申朔日戌寅、高麗王は僧・恵灌を貢ぐ。すなわち僧正に任ず。
同じ僧侶の惠灌が貢がれている。言ってみれば、貢がれるほどの高僧だったということで、すぐに「僧正」という地位についたのだ。では、同じように貢がれた曇徴は、どうなったのか? 奇妙なことに、それについて、やはり一言半句も記載がない。『日本書紀』の推古朝期の記載で、日本へ来た高麗僧たちに関するものは、恵灌のように高い地位を授けられたり、あるいは単に「帰化」したなどと、およそ来日後どうなったかを明記するのが普通。にも拘わらず、曇徴に関してだけはそれがない。高麗王の貢ぎ物ともなれば、より詳細であって然るべきなのだが、それがまったく記載されないのは、通常ではありえないことだろう。
果たして、曇徴は日本へ来たのだろうか? 来日したとしたら、どこへ行ったのだろう? そもそも「法定」って何? 残念ながら、『日本書紀』をひっくり返して読んでも、その答えは見つからない。人間、わからないことには蓋をする。まっとうな史家ほど、この曇徴の記載には触れないようにするだろう。
ところが、昔からすこぶる頭のいい輩はいる。わからないことはそのまま触れずにいてくれればいいものを、見事逆手にとって利用したらしい。
太子信仰と曇徴
推古朝といえば、曇徴などよりはるかに有名な人物がいる。厩戸豊聡耳皇子命(うまやとのとよとみみのみこのみこと)、すなわち、誰もが知る聖徳太子である。太子については、四天王寺や法隆寺など縁の寺院によって、超人的な逸話を含めて喧伝され、太子信仰というものが形成されていった。その太子信仰にとって重要な資料である『聖徳太子伝暦』というものに、次のような文がある。
十八年春三月。高麗僧曇徴。法定二口来。問之以昔身微言。二僧百拝。啓太子曰。我等学道年久。未知天眼。今遥想昔。殿下弟子而遊衡山者也。太子命曰。師等遅来。宜住吾寺。即置法隆寺。
(推古)十八年春三月、高麗の僧曇徴、法定の二口来る。之に問うに昔身微言をもってす。二僧百拝し、太子にもうしあげて曰く、我等道を学ぶこと年久しくも、未だ天眼を知らず。今遥に昔を想うに、殿下の弟子にして衡山に遊ぶ者なり、と。太子命じて曰く、師等来ること遅し、宜しく吾寺に住むべしと。即ち法隆寺へ置く。
う~む、見事としか言いようがない。先に挙げたわからないことが、氷解する。意味不明の「法定」は曇徴同様の僧侶に化け、2人そろって法隆寺に住まわれた。しかも、前世は聖徳太子と師弟関係にあり、3人で中国五岳の一、衡山に遊んでいたという、神話レベルのお話付き。
余りに出来すぎていて、私のような疑り深い人間だと、すぐに眉に唾をつけてしまうのだが、困ったことにこの『聖徳太子伝暦』は、一説には延喜17(917)年に藤原兼輔(877-933)が編んだと言われ、また延喜17年は無理だとしても、相当古い時代に成立し信憑性が高いと信じられた時期があった。流石に現代では、内容的に信用のおけない部分が多々あり、成立年代も明確にわからないとされているのだが、一度信じられてしまうと、それは後々まで影響が残る。特に、『日本書紀』の曇徴の記載のように、それだけだとわからない部分が多いと、わからないと記述するより、信用がおけなくとも『伝暦』の記載を使った方が簡便になる。
と、いうことで、意味不明の「法定」は僧侶に化けたまま、読み下されるのが普通になってしまった。そして、お隣の韓国においては、曇徴は法隆寺に住んでいたのだから、あの金堂の壁画は彼が描いたものに違いない、などという滑稽な説まで膾炙されている。
まったくもって、歴史上の真実を知ろうとすることは、なかなかに難しいし、わからないことをわからないとすることも、難しい。そんな難しいものの1つが、日本の製墨の始まりに関わる曇徴の記録なのだ。ただし、繰り返すが、日本における和墨事始は、曇徴ではないことだけは確かである。

図版出典:宮内庁ホームページ(正倉院)
左 中央 右