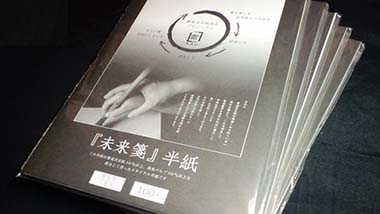現在の高校では、どのような書道教育が行われているのでしょうか。
授業では? 課外活動では? 他教科との連携? 地域との連携?
複数の執筆者によるリレー連載の形式により、
「高校の書道教育の現在」を浮き彫りにしていきます。
現在の高校では、どのような書道教育が行われているのでしょうか。授業では? 課外活動では? 他教科との連携? 地域との連携? 複数の執筆者によるリレー連載の形式により、「高校の書道教育の現在」を浮き彫りに。
第3回は、昨年(2024年)8月に開催された全日本高等学校書道教育研究会の
川崎特別大会について、大会長を務めた荒井利之氏にレポートしていただきました。
高校の書道教育の役割や授業は、どのように研究されているのでしょうか。
さらに、芸術系教科の今後についても考えていきます。
第3回は、昨年(2024年)8月に開催された全日本高等学校書道教育研究会の川崎特別大会について、大会長を務めた荒井利之氏にレポートしていただきました。高校の書道教育の役割や授業は、どのように研究されているのでしょうか。さらに、芸術系教科の今後についても考えていきます。
第3回
授業改善は私たちの永遠の課題
荒井利之(川崎市立高津高等学校教諭)
川崎特別大会
令和6年8月8日(木)、9日(金)に第59回全日本高等学校書道教育研究会川崎特別大会が川崎市スポーツ文化総合センター(カルッツかわさき)にて開催されました。開催テーマとして『「高等学校芸術科書道とは」〜高等学校教育の中における書道教育の役割を改めて考える〜』を掲げ、会期の2日間で延べ600人以上の方にご参加を頂き、無事に幕を閉じることが出来ました。参加された皆様をはじめ、ご支援ご協力を賜りました多くの皆様に心より深く感謝を申し上げます。
この大会は、これまで毎年全国各地で開催されてきましたが、ここ数年のテーマは現行の高等学校学習指導要領の趣旨に則った授業研究や実践発表を通し、これからの書道教育に求められる授業の在り方を探究する場となっています。
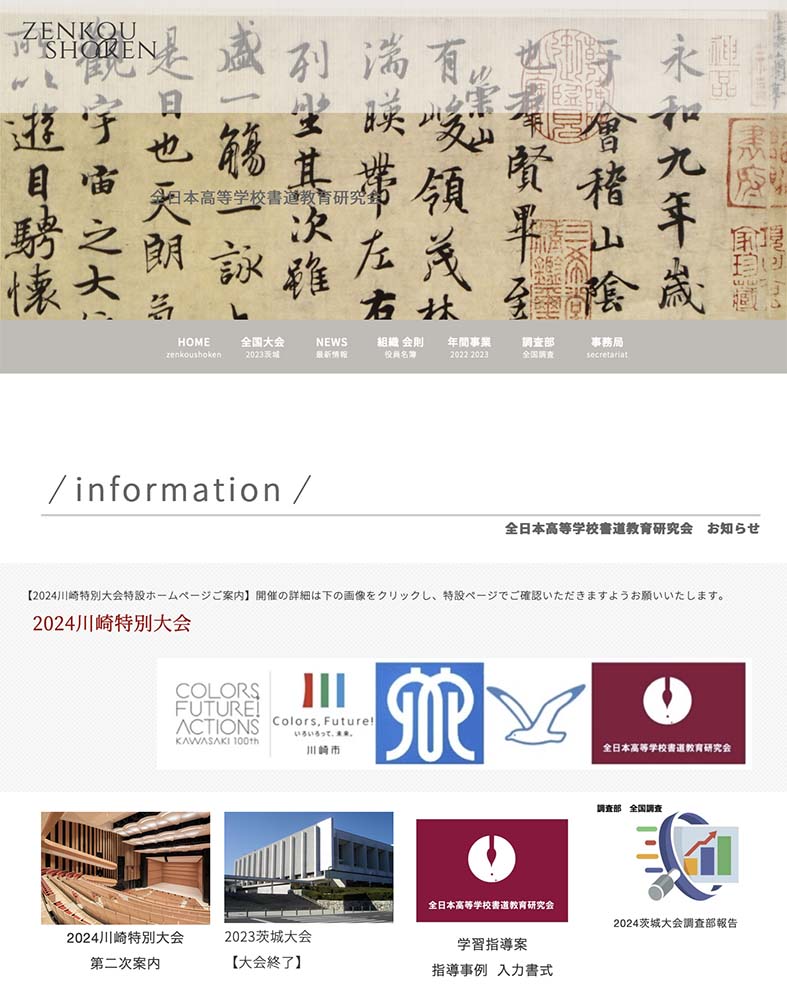
平成30年度に現行の高等学校学習指導要領が告示され、令和4年度から学年進行で実施され今年で3年目を迎えました。今回の改訂では学習指導要領の改訂の趣旨を理解し、新しい学習評価の考え方と、具体的な評価方法に基づいた教育課程の編成、そして主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善、ICT環境・機器等を効果的に活用した指導の工夫に取り組むことが求められています。
これらの内容が全国の高等学校が正しく理解し実施されるよう年2回開催される全国指導主事連絡協議会において文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官から説明を頂く機会があります。そこには各都道府県や政令指定都市から代表者が集まり、そこでの情報を各地の書道教員に周知してくださることで私たちも課題意識を持って授業改善に取り組んでいるところです。
ただ、私たちはこれらの情報を吸収し、自分の授業に生かすだけでは自分がどこまで理解し成長しているかを把握することはなかなか出来ません。そこで先に述べた全国大会を毎年各地で開き、授業研究や実践発表を披露し合い、意見交換を通して参加した先生やこれから書道教員を目指す大学生・大学院生の皆さん一人ひとりの意識を深め、授業改善や心構えに生かして頂く場として大事な機会としています。
今年の川崎特別大会は事務局本部が直接運営を担当しましたが、この機会を生かし様々な取り組みにチャレンジしました。もちろん良き伝統や発表スタイルの長所を生かしつつ、全国の書道の先生方が今求めている情報や取り組みを全面に打ち出すプログラムを構成しました。また、グループ別の研究協議だけでなく、参加者全員で意見交換が出来るシンポジウム形式を取り入れるなど、これからの書道教育に求められている大事なことを共通理解していく場面も取り入れました。そのことで今回の大会ではこれらの成果を上げられたのではないかと思います。
(1) 今求められる書道の授業のあり方を「授業研究発表」を通して参加者全員で共有することが出来た。
(2)「研究協議シンポジウム」ではこれからの書道教育のあり方を多角的に見据え、様々な立場のパネラーによる意見交換を通して課題と解決策を見える化することが出来た。
(3)「ブロック別情報交換」では、各都道府県の研究成果の共有、今後の全国大会開催に向けた情報交換、さらに若手の先生が活躍できる基盤を構築することが出来た。
(4)「授業実践発表」では開催テーマに基づいた内容を協議し、今後の授業実践の礎とすることが出来た。
(5)「チャレンジ分科会」を設け、様々な視点から書道教育を取り巻く諸課題を見つめ、課題意識を持って授業や研究に取り組む機会となった。
また、開催期間を従来の10~11月の平日開催から、夏休みに変更したことで参加された皆さんから多くの賛同を頂くことが出来ました。何よりこれから書道教員を目指そうとする大学生や大学院生、さらに大学関係者、企業の方などが多く参加され、書道教育の現状をご理解いただくことが出来たことは次世代につながる貴重な機会となりました。
今後は、さらに多くの先生方に参加していただけるためにも周知の工夫をするとともに、研修になかなか参加出来ない非常勤講師の先生方にも参加して頂き、これからの書道教育の在り方を共有していきたいと考えています。
私自身もこの全国大会には書道教員になった約40年前から何度も参加させて頂き、多くの学びを頂きました。発表される先生方の研鑽を重ねた発表を目の当たりにし、ワクワクしながら翌日からの授業に取り入れたものでした。これからも参加される皆さんにとって明日からの授業等をさらに高めたい気持ちにさせる活力ある全国大会であり続けることを願ってやみません。

これからの時代に求められる芸術系教科
過日、文化庁より文化芸術教育の充実・改善に向けた検討会議における論点整理が示され、これからの時代に求められる芸術教育の在り方や可能性について述べられています。
その中には、これからの時代に求められる芸術系教科は、将来にわたり書の見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の書や書文化等と豊かに関わることの出来る資質・能力を育てることだと示されています。
そして、芸術系教科の学びは、美を追求し表現しようとする人間固有の営みとも言え、答えを自らつくりだしていくものです。授業では作品制作に向けて何度もトライアンドエラーを繰り返し、自己決定を積み重ね、自己実現を図ることで様々な単元を通して見方・考え方を養っていきますが、多様な価値を認め合うことで柔軟な感性を身に付け、創造的な思考力や全体を俯瞰する構想力、判断力、コミュニケーション力などの育成にもつながっています。
常に時代が変化し続ける中、私たちが向き合う課題は決して答えが用意されているものばかりではありません。自ら問いかけ課題を解決していく力、自ら意義や価値を作り出していく態度がますます求められる中、芸術教育はまさにその資質・能力を養う絶好の機会だと言えるでしょう。
芸術系教科はこれまで表現の巧拙に評価の主軸が置かれがちだったり、芸術に対して才能や興味関心のある人たちによる世界と捉えられやすい傾向もあります。しかし、学校教育における芸術系教科の意義は、知性では捉えらえないことを身体を通して、知性と感性を融合させながら捉え、新しい意味や価値を創造し、自己を形成していくことにあります。
そして芸術教育を通した学びは、全ての教科等において通底する「創造」の土壌とも言えましょう。このような教科の特質を生かすためにも、国語科との連携はもちろん、科学や技術などの理系分野との連携の可能性も考えられます。
私たちは芸術系教科に携わる者として、専門分野を深める学習だけでなく、表現や鑑賞の学習を通して養われる生徒の資質・能力が学年や学校段階を越えて円滑に接続されることが大事であり、言い換えれば芸術と社会がつながる中で存在感をますます発揮出来るのではないかと感じています。
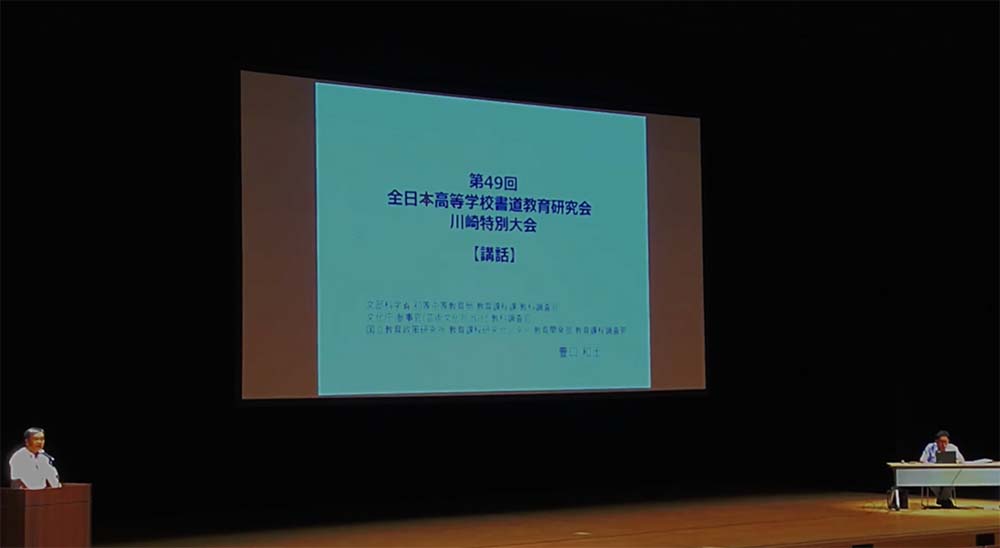
YouTubeで公開されている