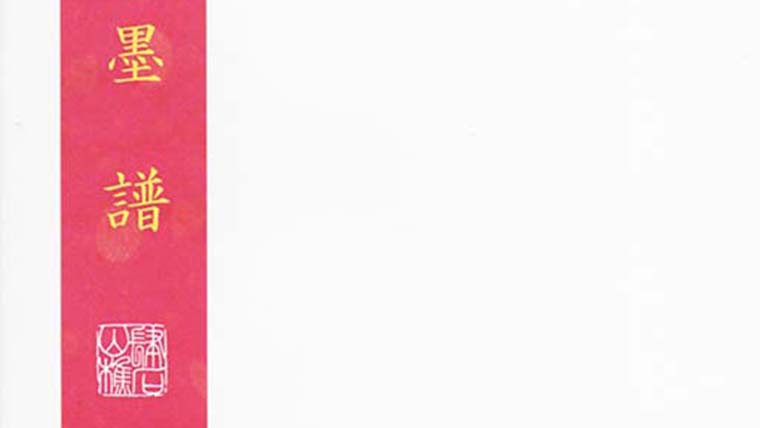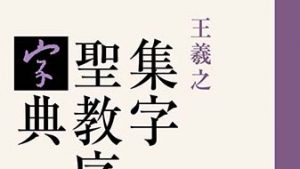未来を見据える目と行動力で、新時代を切り開こうとする50歳世代に焦点を当てた新シリーズ。
インタビューを通して、人生100年時代の折り返し地点にあるかれらの過去、現在、そしてあるべき未来像にエールを送る。
未来を見据える目と行動力で、新時代を切り開こうとする50歳世代に焦点を当てた新シリーズ。インタビューを通して、人生100年時代の折り返し地点にあるかれらの過去、現在、そしてあるべき未来像にエールを送る。
vol.4 金敷駸房

(近影 ©IZUMI IWAKI)
文/西村修一(書道評論家)
2025年の新春早々、東京の最新の商業、文化施設として注目される麻布台ヒルズ内にある大垣書店で、金敷駸房の新作が紹介された(「金敷駸房@大垣書店」2025年1月3日~7日)。
書店の奥まった空間に幅4メートルの大作「美響」がどっしりと構えている。濃墨の強い線で太細、潤渇を巧みに交えながら、作品左下の先の方に収束点を設けることよって、鑑賞者に立体感や余韻を感じさせる構図となっている。文字から線質の追究、その結果「余白の美しさ」を考えているという、近年の金敷作品の真骨頂とも思えた。
実は大作はこの一点だけで、筆者としては物足りなさを感じたのだが、会場が通常営業をしている書店を使っているので、止むを得ないのだろう。代わりに、そこここにある書架の空きスペースには、一辺が40センチほどの真っ白なボックスや、様々なデザイン形状の小さな白板を舞台にして、金敷は自在に筆をふるっていた。デザイナーとの協業によって、書作品をモダンなインテリアアートとして提案しているようにも見えた。

金敷駸房作品展@大垣書店 2025
(大垣書店麻布台ヒルズ)

金敷駸房作品展@大垣書店2025
(大垣書店麻布台ヒルズ)
さて金敷がこうした額装、軸装形態だけに拘らない多様な演出志向の個展を開いたのは、今回が初めてではない。2009年にはタワーホール船堀で「過剰」、2014年にはシアター1010で「カナシキシンボウ展 ANVIL」というタイトルで、鉄材や木工と書の融合を試みた個展を開いている。2018年には東京都美術館が企画した「見る、知る、感じる――現代の書」展の出品作家6人のうち1人に選ばれ、既成の書作品発表の枠を超えた演出で注目を集めた。
筆者が初めて金敷作品に出合ったのは、2014年のANVIL展だった。単に書作品を並べるだけでなく、鉄製の部材などを配した空間の中に、書作品を重層的に配していた。中でも印象的だったのが、村山槐多の『槐多の歌へる』の全文を、全長約5000メートルの紙に一行書きで延々と記した「槐多の瀧」だった。この時は瀧というよりは、長い紙を激しい奔流のように随所で括るような演出だったが、4年後の都美術館の展観ではバーを使って流れ落ちる瀑布のようなイメージに変容させた。


見る、知る、感じる──現代の書 2018 (東京都美術館)

全長5000メートルに及ぶ壮大な作品
すでに2010年に第13回國井誠海賞を受賞していた金敷は、こうした新機軸への取り組みを評価されて2019年には第13回手島右卿賞を受賞し、書壇でも注目される存在となった。しかしながらその一方で彼は、自由な創作活動に専念するために、これまで参加していた毎日書道展、創玄書道会を離れ、フリーの書家となったのである。テレビの大河ドラマの書道指導や数多くの芸術イベントにも参加し、協業によるアート作品づくりの世界に加わっている。合間を縫って、2022年8月には銀座の蔦屋書店で、同年9月には渋谷Bunkamuraのギャラリー(既報)で、今回の大垣書店のような書中心の創作活動も続けてきた。


詳細はこちら

金敷のこうした創作活動のエネルギーは、どこから湧き出ているのか。少し時計を遡ると、見えてくるものもある。金敷が書道に出合ったのは、千葉在住の小学4年生のころ。兄2人はそろばんのお稽古に通ったが、算数が苦手だったという彼は、習字の塾を選んだ。中高とスポーツと習字の二刀流を続けた。そして高校2年生の時、書道の指導教師が転任することになり、紹介されたのが石飛博光だった。
これが、運命の出会いだったのではないか。もちろん金敷は、当時は書を生涯の生業にしようとは思っていないし、なれるとも思っていなかった。むしろ、演劇の世界にあこがれ、千葉から上京した動機も舞台に上がるためだった。しかし、演劇の道はなかなかに厳しく、一方で石飛の書に惹かれながら、書の道は次第に開けていく。30歳の時、退路を断って書道で独り立ちすることを決断した。
金敷の書は、もちろん30年以上にわたって師事している石飛博光の線質、作品作りを何処かしら感じさせるものがある。微塵も隙を見せない線。そのための題材、文字選び、細かく見れば行間の間(ま)の取り方、黒と白による余白の美の生み出し方、「石飛先生の書が大好きだ」というだけに、憧憬に近いものがあるのだろう。
しかし、展覧会での演出には金敷独自の個性も見え隠れしている。おそらく、ひとつは家業の鉄材の加工製作に幼いころから親しみ、培われた造形のセンスだろう。さらに学校では、演劇など人に見せて楽しんでもらうのが好きだったという、青春期からの芸術志向、表現活動への強い思いが、書の個展でも表出してきたのではないだろうか。


この書作の道と空間演出をどう組み合わせ、発展させていくのか。「人生は辛抱だ」といって、若き彼に千葉・房総の「房」と、駿馬を意味する「駸」を組み合わせた号をくれた石飛に、どう答えるのか。石飛がよく口にするのは「わたしの師である金子鷗亭は『師を否定しろ』というのが口癖だった」である。では金敷は、師石飛をどう否定し、超えていくのか。これからも見守っていたい。
金敷駸房(かなしき・しんぼう)
1973年、東京都大田区生まれ。石飛博光に師事。現在はフリー。個展多数開催。テレビ・映画の書道指導も多く、2025年の大河ドラマ「べらぼう」の書道指導も担当。三駸書道会主宰。
◉写真提供/神田昇和
◉金敷駸房公式サイト
墨ザル https://sumizaru.jp